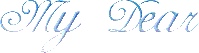 |
|
|||||
| ▼Contents | Top | MIDI | BMS | PC | Yukyu | Profile | Diary | BBS | Site Map | Mail | Link | | ||||||
| ▼Directory Top Page > Yukyu Page > Data Page | ||||||
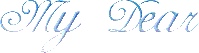 |
|
|||||
| ▼Contents | Top | MIDI | BMS | PC | Yukyu | Profile | Diary | BBS | Site Map | Mail | Link | | ||||||
| ▼Directory Top Page > Yukyu Page > Data Page | ||||||
後期にかえて‥‥ 「さくら亭にて・番外編」
カララン‥‥。
「こんにちは」
おなじみさくら亭の扉が開き、シェリルが入ってきた。
「ああ、いらっしゃい‥‥」
パティがいつものように明るく迎え‥‥るかと思いきや、どよ〜んとした元気のない笑顔をいきなり向けてきたので、シェリルはびくっと身体を震わせた。
いったい何があったんだろう?
「ど、どうしたんですか?」
と聞く、シェリル。
それに対しての、パティの答えは
「ああ。ほら、あそこのひとよ‥‥仕事ぶりが悲惨でさぁ。見てるこっちがかわいそうになっちゃうのよ」
であった。
見ると、一番隅の暗〜い席で、ひとりの男が、なにやらウンウン唸りながら、物を書いていた。いったいいつ床屋に行ったのかよく分からないようなボサボサの頭をした、いかにも、うさんくさい男である。
「最近、エンフィールドに越してきたの。街の脚本屋だってさ」
「ええッ?」
とたんに、シェリルの頭がぱっと輝いた。彼女は物書き志望だったので、そういう職業の人に憧れているのである。そこで彼女は、パティの制止するのも聞かずに、街の脚本家のそばに寄って行った。
「あ、あの?」
「んん?」
脚本家は、いきなり声をかけられてびっくりしたようだった。さらに、声をかけてきたのがかわいらしい少女だったので、二度びっくりした。
彼は、実は人見知りが激しい性格のため、こんな風に女の子が話しかけてくることなど、めったにないのであった。また、そういう性格だから、こんな怪しげな職業についているのであった。
「何か用かい、お譲さん?」
脚本家は、キンピカデーハーな女性より、シェリルのような、質素で飾り気のない女の子が好きだったから、ニコニコしながら返事をした。
実際のところ、彼は今、同時に五本の作品を書き上げなくてはならないという危険的事態に陥っており、先ほども、A社から催促の電話中、「はいはい、ただいまやっております」と答えながら、B社の原稿をかいていたという、とんでもないことをやってのけていたばかりなのだ(しかもそれは、M社の宣伝部のS谷おねーさんにはすっかりばれていたりするのだった。頼む、K村さん。ばらさないでくれい。)
しかし、そんな状況でも、彼は、目の前の三つ編みの女の子とお話する方がずっと楽しく思えたので、愛用のノートパソコンのスイッチをプッチリと切ってしまった。
「あ、あの、私、シェリルといいます。その‥‥実は、小説家になりたいんですけど‥‥。
「はい。じゃあ、これ」
「は?」
シェリルは、いきなり企画書の束を渡されて、面食らった。
「あの‥‥?」
「書いて書いて。ギャラは全額あげるから」
「いえ‥‥でも‥‥いきなり、そんな‥‥」
「合格。君みたいな子なら、即、採用」
「そんな、いい加減な‥‥」
シェリルは、ドギマギして、企画書を押し返す。
脚本家は、そんなシェリルの様子がますます気に入ったので、絶対に「嫁さん」‥‥
じゃなかった‥‥「助手」にしようと決めた。
だが‥‥その時
バターン
扉が勢いよく開き、C社とD社とE社のディレクターが、鬼のような形相で、飛び込んできた。居場所がついにバレたのだ。
「うわぁッ」
脚本家はあわてて逃げ出そうとしたが、後の祭りである。
その後に繰り広げられた惨劇は、あまりにも恐ろしくてここに書くことはできないが、それを間近で見ていたシェリルが、あまりのショックに三日間寝込み、「もしかしたら、小説家になるのはよした方がいいかもしれない」と考えたことだけは、記しておこう。
ちなみに、その後、街の脚本家がどうなったかは誰も知らないが、ここにこうして本ができ上がっているところをみると、まだ、エンフィールドのどこかでウンウン唸っているのは確かなようである‥‥。
(1997年6月某日。「悠久」ラジオドラマの収録中に記す)
「さくら亭にて・番外編2」
けだるい午後の日差しの中。
カララン‥。
おなじみさくら亭の扉が開き、これまたおなじみの小説家志望少女、シェリル・クリスティアが入って来た。
「こ、こんにちは、パティちゃん」
「あら、いらっしゃい」
パティは、厨房の中で夕食時に向けての仕込みをしていたが、その手を止めて、店内のカウンターに出てきた。
「今日は紅茶にするの?それともコーヒー?」
「え、えっと‥‥紅茶を‥‥」
「オッケー。ちょっと待ってね」
パティが湯をコンロにかけ、今日のおすすめのお茶のセットを手際良く用意していく。
シェリルはこのところ毎日のようにさくら亭を訪れては、窓際の席に座り、趣味の小説を書いているのだ。それで、パティの方も「そろそろ来る時間かな」‥とあたりをつけて、準備をしていたらしい。
「あ、あの、‥パティちゃん?」
「うん?」
シェリルにおずおずと声をかけられ、パティは顔を上げた。
「なぁに?」
「‥‥最近‥‥見ないですね」
「誰を?」
「街の脚本屋さん」
「しーッ しー、しーッ」
パティは、とたんに手を口に当てて、シェリルの言葉を遮った。そして、恐る恐るあたりを見回す。
びっくりしたシェリルは小声になって、
「ど、どうしたんですか?」
「軽々しく知り合いだなんて言っては駄目よ。あの人、今、暗殺ギルドのブラックリストに載ってるんだから」
「えええッ?」
シェリルは、信じられないというような顔をした。たしかにうさんくさい話ばっかり書いている脚本屋ではあったが、そんな大それたことになっているなんて‥‥?
「なんでもね‥‥例の悲惨な仕事ぶりに拍車がかかっちゃって、とうとう、あっちこっちに迷惑かけまくってるらしいのよ。怨まれちゃって、もう大変」
「まぁ‥‥」
「毎度毎度、『今回の仕事のスケジュールこそ、人生最大の危機』とか言いまくってたけど‥‥最近はそのスローガンが、『今回の仕事が終わるとしたら、それはもう人生最大の奇跡』に変わっちゃて‥‥」
「‥‥」
「そういえばここんとこ、電話にむかって『うう、えろうすんまへ〜ん。明日までには必ず‥‥』以外の台詞を言ってるとこ見たことがないわねぇ。‥‥もともと、締め切りを守るだけがただ一つの取り柄だったのに」
パティはやれやれとため息をついた。
そんなパティの様子を見ながら、シェリルはポツリと言う。
「なんか‥‥やけに詳しいんですね?」
「えっ?ええっと?そんなことないけど‥‥?」
「もしかして、パティちゃん。このさくら亭に‥‥街の脚本屋さんをかくまってるんじゃ‥‥」
パティは、うっ‥‥という顔つきになった。とにかく嘘をつくのが苦手な子なのである。
「ふ〜ん。そう。ここにいたんですね?へぇ〜」
シェリルが途端に、怪しい笑みを浮かべた。
「シェ‥‥シェリル?」
「ふ。ふふふふ‥‥フフフフ‥‥フハハハハハーーーーッ」
シェリルだったはずのその人は、またたくまにその姿を異形に変え、暗殺者と化した。パティがギョッとなってあとずさる。
暗殺者は、パティが抵抗しないのを見極めるとすぐに、さくら亭の二階に駆け上がり、脚本屋が潜んでいると思われる部屋にバターンと飛び込んだ。
「むっ?」
室内を見回す暗殺者。 すると‥‥そこには
(来月発売の
vol.2に続く‥‥って、続くの本当に?)
by 脚本家 滝本 正至 (たきもとまさし)
「さくら亭にて・番外編3」
「‥‥暗殺者は、パティが抵抗しないのを見極めるとすぐに、さくら亭の
2階に駆け上がり、脚本家が潜んでいると思われる部屋にバターン!と飛びこんだ!(むっ?!)室内を見回す暗殺者!すると‥‥そこには!!!」
「そこには?!」
「そこには‥‥ッ!」
「だから、そこには?」
「そこには‥‥ええっと‥‥そこには〜‥‥ううーんと‥。そうだなぁ?どうしよう?」
「だ〜〜。‥‥ちょっと、あんた!いったい何よ、それぇッ?!」
ここは、おなじみさくら亭。時刻は、そろそろ月が中天にさしかかる頃合いである。
もうじき今日の営業時間を終えようとしている店内は、あの夕食時の戦のような喧燥からは想像できないくらい、穏やかでのんびりしていた。やや照度を落としたランプの灯が、あと数組しか残っていない客の、それぞれの就寝前の時間 例えば本を読んだり、手紙を書いたり、親しい友人と語り合ったり をやさしく照らし出している。
だが!
だが、しかし!
カウンター席の一番奥で、たった今、パティに呆れ声をだされた彼だけは、ちょっと事情が違っていた。ノートパソコンを開いたっきり、かれこれ 2時間以上もウンウン唸っているのだ。
「ねぇ。脚本屋さん。なんでオチもきめてないのに「次回に続く」なんて書いて出しちゃうわけ?だから、後で困るんじゃないの!」
パティは、約1ヶ月前に発売になった「 Vol.1」のCDのブックレットを突き出しながら言った。
「だ、だって仕方ないだろう。あの時は、その‥‥1ヶ月もあれば続きを思いつくと思ったんだから‥」
彼は、うらめしそうにパティを見た。だが、パティは同情の余地なしという顔で、
「あたし、これ以上あんたの事かくまうのヤだからね。特に、 S社の渋Yディレクターといえば、いつもニコニコしてるけど、実は、あの千葉繁さんですら逆らえないという伝説の‥‥」
「わーッ!わーッ!それ以上言うな!危ない!」
街の脚本家はあわててパティの言葉をさえぎった。
そして、今の爆弾発言で、本当に暗殺ギルドの刺客が送り込まれてこないかどうか確かめるように、窓の外をうかがった。
「あ、あの御方に、そんな事を言ってはいかん。いつも世話になっているのだ」
「そう思うんだったら、早く仕上げなさいよ。その原稿、一昨日が締め切りなんでしょう?」
「ううう、確かに。‥でも、書けないものは書けないし。うう〜む‥‥」
そして、更にしばらくのあいだ唸っていたが‥‥ややの後‥‥。
「仕方がない。今夜は仮病になろう。寝る。」
「ね、寝るって ちょっとォ!」
パティは驚いて、2階へ上がっていこうとする脚本屋の袖口をつかんだ。
「まちなさいってば、ねぇ!」
「ええい、離せッ。我が輩はお子様なので、眠くなったら寝るのだ!」
「そんなムチャクチャな!」
「ムチャでもなんでも、寝ると言ったら、寝‥‥」
と、その時!
ティリリリリ‥‥!
いきなり脚本屋の携帯電話がなった。彼は、青くなって、すかさずそれをパティに押しつける。
パティは、仕方なくその電話に出た。
「はいはい。あ、どうも、こんばんは。‥‥え?脚本屋さんですか?ええっと‥‥その‥‥」
脚本屋は、自分の方をチラリと見たパティに向かって、おもいっきり大きなバッテン印を出す。
すると彼女は、ニッコリと微笑んで‥‥こう言ったのである。
「ええ!ここにいますよ!なんなら、逃げられないようにロープで縛っときましょうかッ?!」
「げげげ〜〜ッ!?」
ちなみに、数時間後。ロープでグルグル巻きにされた脚本屋は、ムチでビシバシされながら、この原稿を完成させなんとかブックレットの印刷は間に合ったという‥‥。
(追伸:このドラマはフィクションであり、悠久幻想曲及び実在の人物団体には、一切関係ございません) (
END)
〜Top〜
〜Back〜